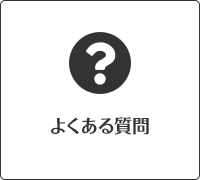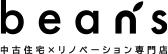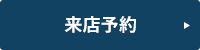ふと思い立って京都府北部にある伊根町を訪れました。
伊根町といえば、海にせり出すように立ち並ぶ木造の家々
あの風景を一度は見たことがあるという方も多いかもしれません。
けれど、実際に現地を訪れてみて初めて分かること、感じることがたくさんありました。

■ 伊根湾の地形がもたらす、穏やかな海との暮らし
伊根の船宿が成り立ってきた背景には、伊根湾の特異な地形があります。
まず驚いたのは、日本海側でありながら、海が南に面しているということ。
これはかなり珍しく、冬の北風や荒波の影響を受けにくいのだそうです。
さらに、湾の外側には「青島(あおしま)」という無人島が浮かんでおり、これが天然の防波堤のような役割を果たしています。そのため、一年中波が穏やかで、高潮の被害もほとんどないとのこと。
目の前が海なのに、そこに暮らしがあるという不思議。けれどそれは、自然との絶妙なバランスによって守られているのだと実感しました。

■ 船宿の正体は“海のガレージ”
「船宿」と聞くと、旅館や民宿を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、伊根の船宿の本来の役割はまったく違います。
実際には、海と接する建物は船の格納庫(船置き場)としての“倉庫”。
漁船や小舟を収納したり、漁具を置いたりと、海仕事の拠点として使われてきた建物です。

住まいはというと、道を挟んだ山手側にある母屋で暮らすのが一般的。
つまり、伊根の生活は、海と陸の二拠点で構成されているというわけです。
その間には狭い道路が通っていて、海→船宿→道→母屋という並び。生活の中に海がある、そんな暮らしが今も自然に営まれているのです。
古い舟屋をリノベーションした民宿やカフェから見る伊根湾の眺めを楽しめることもおすすめです。

■ 昔ながらの“将棋のコマ型”の建築
今回、古い船宿も見学させていただく機会がありました。特に印象に残ったのは、建物の断面が“将棋の駒”の形をしている建物があるという点。
これは、船を収納するスペースの開口部を広く確保するための設計をするために、土台付近の柱は広がって2階付近は狭くなっている構造。シンプルな見た目の中に、漁師の知恵と美意識が凝縮されているように感じました。

■ 最後に:暮らしと自然が調和する町
伊根の風景は、ただの“観光地”ではなく、今も人が暮らし、働き、生きている場所です。
派手さはありませんが、海とともに生きるその姿は、私たちが忘れかけている「自然との距離感」を思い出させてくれます。
都会の喧騒から離れ、静かに流れる時間の中で、ふと立ち止まって自分の暮らしを見つめ直す――
そんな旅をしたい方に、伊根町は心からおすすめできる場所でした。