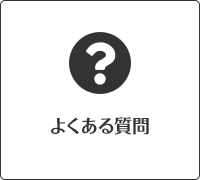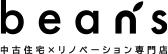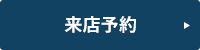「毎月の家計で一番大きな固定費は?」と聞かれれば、多くの人が「家賃」や「住宅ローン」と答えるのではないでしょうか。
住居費は一度決めてしまうと、なかなか減らすことができない固定費。だからこそ、最初に「無理のない範囲」を見極めておくことがとても大切です。
この記事では、手取り収入に対してどのくらいの住居費が適正なのか、そしてライフスタイル別の考え方をわかりやすく解説していきます。

一般的な目安は「手取り収入の25〜30%以内」
ファイナンシャルプランナーや家計管理の専門家がよく挙げる基準は、
住居費=手取り収入の25〜30%以内です。
例えば、手取り収入が25万円なら住居費は6万〜7.5万円が目安。
手取り30万円なら7.5万〜9万円が妥当といえるでしょう。
もちろん、この「25〜30%」という数字はあくまで平均的な目安です。
実際には家族構成や将来のライフイベントによって調整が必要です。
ライフスタイル別「ちょうどいい住居費」
① 単身者の場合
一人暮らしでは「交通アクセスや生活利便性を優先したい」という人も多いでしょう。
娯楽費や交際費にお金を回す余裕を残すなら、30%程度までなら許容範囲。
② 子育て世帯の場合
教育費・食費・車の維持費など、支出が増えるのが子育て期。
このタイミングで住居費が重すぎると家計が圧迫されやすくなります。
無理のない目安は25%以下。余裕を持たせておくと安心です。
③ 40代以降・老後を見据える世帯
住宅ローンを抱えている人も多い年代。
同時に教育費のピークや老後資金の準備も始まるので、20〜25%以内が望ましいとされています。
「返済可能額」より「生活に無理がない額」で考える
住宅ローンを組むときに銀行から「あなたは◯◯万円まで借りられます」と言われることがあります。
しかし、この金額はあくまで「返済能力の上限」。
生活を楽しみながら返済を続けられるかどうかとは別問題です。
ボーナス払いを前提にした返済や、ギリギリの金額でローンを組むと、教育費や老後資金が足りなくなりがちです。
「借りられる金額」ではなく「無理なく払える金額」でシミュレーションすることが大切です。
固定費全体のバランスを意識する
家計を健全に保つには、住居費だけでなく固定費全体のバランスを見る必要があります。
-
住居費+通信費+保険料
この合計を手取り収入の50%以内に抑えると、食費・教育費・貯蓄に余裕を回せる家計になります。
例えば、手取り30万円の家庭なら、固定費合計は15万円以内。
その中で住居費を7.5〜8万円に収めると、バランスの良い配分になるでしょう。
住まいにかかる「維持費」も忘れずに
賃貸は家賃だけですが、住宅を購入すると以下の維持費がかかります。
-
修繕費:戸建てなら屋根や外壁の塗装、マンションなら修繕積立金。目安は建物価格の1〜2%を年間で確保。
-
火災保険・地震保険:災害リスクに備える必須費用。年間数万円。
-
固定資産税・都市計画税:毎年1月1日時点の所有者に課税される。一般的に年間10〜20万円程度。
購入時は「ローン返済額+維持費」でシミュレーションすることが欠かせません。

家計を守るためのチェックポイント
-
今の住居費が25〜30%を超えていないか?
-
教育費や老後資金のための貯金を確保できているか?
-
収入が減っても支払いを続けられるか?
-
引っ越しや借り換えで改善できる余地はないか?
これらを定期的に見直すことで、家計のバランスを保ちやすくなります。
まとめ:理想は25%、限界は30%
無理のない住居費の目安は、
-
理想は25%以内
-
限界は30%まで
広い家や立地の良さに惹かれる気持ちは自然ですが、住居費を抑えることで得られる心の余裕と家計の安心感は何にも代えがたいものです。
住まい選びの基準を「今の生活」だけでなく「未来の生活」まで含めて考えることが、無理のない家計をつくる第一歩になります。